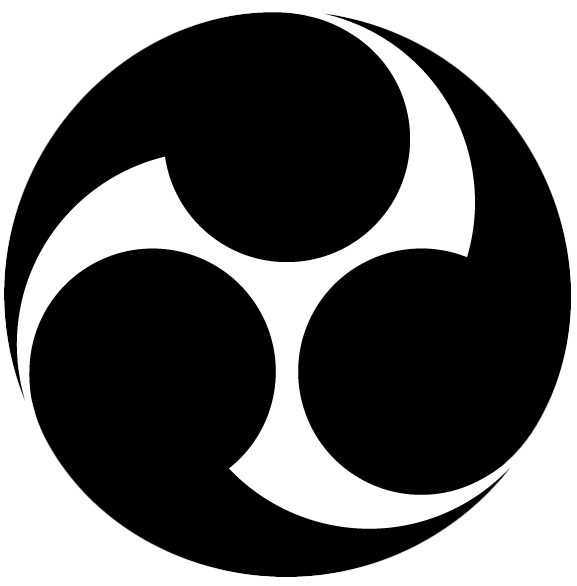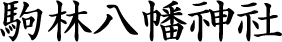安楽寺
安楽寺の概要について
- 所在地
- 埼玉県ふじみ野市駒林866-1
- 宗派
- 天台宗(本山は灌頂院)
- 本尊
- 阿弥陀如来坐像(江戸時代・木造・市指定文化財)
- 他の仏像
- 薬師如来坐像(江戸時代) 十二神将(江戸時代)※「新編武蔵風土記誌」によれば、本尊は立像とされ、他に聖徳太子作の十一面観音像が記されている。
- 行事等
- 4月8日 釈迦祭
4月17日 観音講
8月15日 施餓鬼
安楽寺の歴史について
明治時代に旧福岡村(ふじみ野市上福岡地区の前身)から埼玉県に提出した寺院明細によれば、正式には大林山観量院安楽寺という。 伝承によれば、室町時代中期の寛正4(1463)年に円祐法印という僧侶によって開かれたという。残されている住職の墓石で最も古いのは、 江戸時代前期の延宝3(1675)年の3代目豪信のものなので、少なくとも江戸初期まで遡れそうである。
寺の開基については不明であるが、境内からは南北朝時代の応安7(1374)年の宝篋印塔(ほうきょういんとう)(一部)が発見されたり、 寺の西方には板碑(いたび)も含めた中世の墓の跡などが確認されたりしており、中世に当地に住んだ人々の信仰生活を伺うことができる遺物・遺構がある。
埼玉県の川越は天台宗の勢力が中世以来強く、喜多院・中院・灌頂院が多くの末寺・門徒寺院を抱えていた。川越市からふじみ野市、富士見市中部まで 天台宗寺院が多く分布している。開基の「法印」の称も天台・真言の密教系統のものと思われる。
江戸時代は寺請(てらうけ)制度により、旧駒林村の約半数を檀家としており、八幡神社・鷺宮神社・神明社・第六天・山神社・稲荷社(三社)・富士塚を所有していた。 住職も、庚申講を組織して江戸時代前期の延宝4(1676)年に庚申塔を建立するなどしており、寺の施設自身も様々な用途に使われたようである。