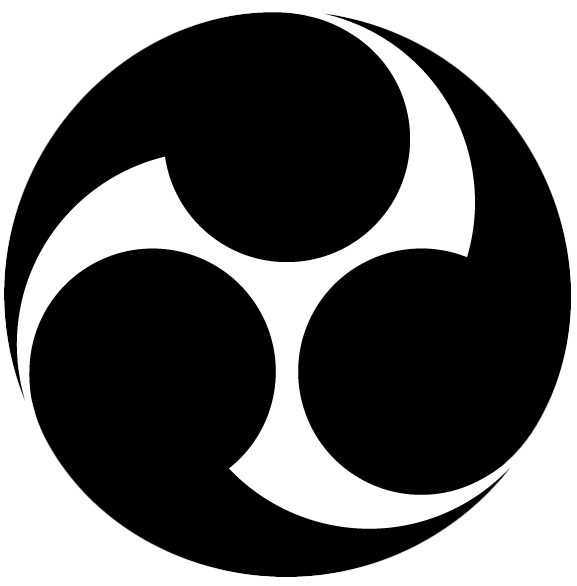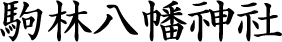官幣大社とは
大きな神社の入り口に、「官幣大社」などと書かれた石塔が立っているのをよく見かける。これは、現在では有名無実となっているが、昭和二十年(1945)の終戦までは社格を示すものとして重要な意味をもっていた。
神社のランキングの歴史は古く、平安時代にまでさかのぼる。我が国では、奈良時代までは中国の律令制度を取り入れて、中央集権国家の枠組みができあがった。当時は祭政一致(政治と神社のまつりごとが一体となっている)が大原則だったので、朝廷を中心とする集権国家体制を維持するには、神社の管理が重要な意味をもっていた。
そして、平安時代に作られた「延喜式(えんきしき)」という律法書の中で、明確な神社の格付けが行われ、官幣大社などといった名称が登場したのである。
このような神社のランキングは、鎌倉時代まで国家の手で管理維持された。しかし、室町時代になるとしだいにその意義が薄れ、応仁の乱(1467〜77)以降は有名無実のものとなった。
明治元年(1868)には、維新政府は「政祭一致」を掲げて、神道を国教化した。そして明治四年には「延喜式」に基づいて官国幣社の制度を復活し、全国の神社は再び国家の管理下に置かれることになった。
旧制度では官国幣社は大社と小社に別れていたが、新制度ではこれを大社・中社小社に分けた。また、国家に特別の功労のあった臣下などをまつる神社を別格官弊社とし、官幣小社に準ずるものとした。
豊臣秀吉を祭った豊国神社や徳川家康を祭った日光東照宮、数百万の英霊を祭った靖国神社などが別格官幣社として格付けされた。そして、官国幣社の祭祀料(儀式にかかる費用)は国費で賄われた。
また、官国幣社、別格官幣社以外の神社は諸社とされ、「府県社」「郷社」「村社」「無格社」など細かいランク付がなされた。現在でも稀に郷社や村社などの名称を耳にするが、戦前までのランク付の名残である。ただし、伊勢神宮は社格を超越して、すべての神社の上に立つものとされた。
しかし昭和二十年に終戦を迎えると、このような神社制度が軍国主義の温床となったという観点から、GHQ(連合国軍総司令部)によって神道指令(これにより、明治以来続いた国家神道は解体された。一説によるとマッカーサーを最高司令官とするGHQは、日本から神社を一掃することを意図したといわれている。)が出された。
これによって、神社は国家の統制から解放されたが、同時に国からの一切の支援が打ち切られた。そして、官幣大社をはじめとする名称もなくなった。けれども、冒頭に述べたように今でも社格を刻んだ石塔などを残している神社も少なくない。
神社とまつりから