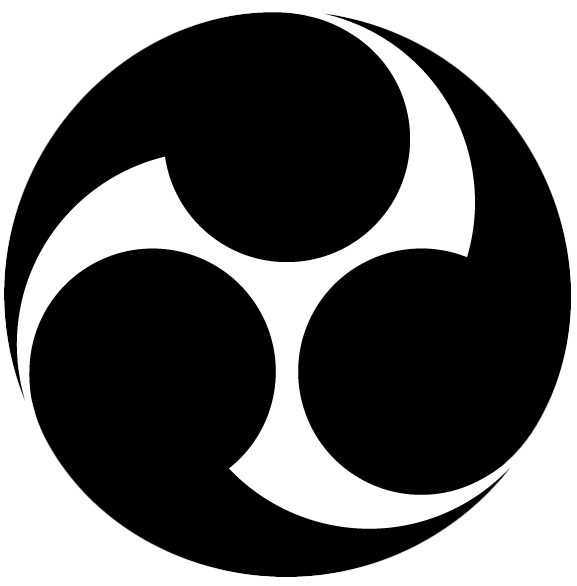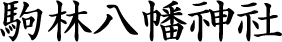駒林村地頭の小栗氏について
出自については、江戸時代後期に幕府によって編纂された系図集「寛政重修諸家譜(かんせいちょうしゅうかふ)によれば、小栗氏は坂東八平氏の流れをくみ、平安時代以来、常陸国(茨城県)小栗御厨(おぐりみくりや){伊勢神宮領地}に拠点を構える武士であった。 時期は不明であるが、三河国(愛知県東部)に移住し、小栗正重の代に至って徳川家康の家臣になったという。松平一族の中には小栗氏と縁戚関係を結び、家康の父親の広忠の代から中堅クラスの家臣として活躍した小栗吉忠(母方に改姓)がいるなどしていることから、徳川家との関わりはもう少し遡るかもしれない。
駒林村地頭になる小栗氏の初代は久勝で、永禄11(1568)年に家康に初めて仕え、当時家康が拠点としていた遠州(静岡県)浜松周辺などに家臣として領地を与えられていた。後に大坂冬・夏両度の陣に活躍し、上総国(千葉県)・相模国(神奈川県)に500石の領地を持つ幕府旗本になった。
駒林村(200石)を初めて領地としたのがその子の久玄(ひさはる)で、前記の領地と合わせて700石を与えられた。駒林村を与えられた時期は不明であるが、同クラスの中下級旗本の布施五兵衛や榊原八兵衛が、福岡村(ふじみ野市上福岡地区の前身)の領地を徳川秀忠から与えられたのが寛永年間(1624〜44)のことなので、おそらく同時期ではないかと考えられる。久玄はその後甲斐国(山梨県)に500石を加増された。
その後の小栗氏は久弘(ひさひろ)、久倫(ひさとも)と続くが、久輪の代の元禄11(1698)年に武蔵国・相模国の領地に移し替えられた。ここに駒林村は川越藩領に編入されることになるのである。